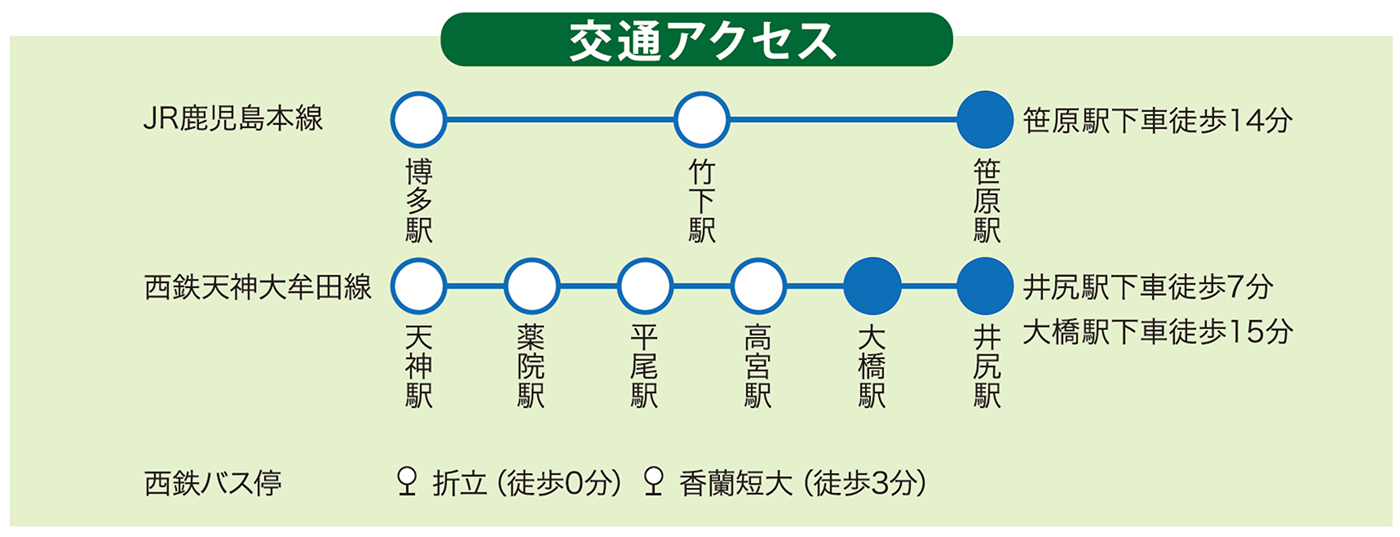遺留分・遺留分侵害額請求権

遺留分・遺留分侵害額請求権
遺留分とは、被相続人の財産を相続するに際して一定の法律上保証されている遺産の最低割合のことを指します。
残された相続人の生活保障であり生計一にしている方を守るための制度となっております。
遺留分は遺言書より優先されるため、遺言書で相続する財産がなくとも、その権利を主張できます。
例外として兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分を主張することができません。
計算方法としては、相続分の半分を遺留分として計算します。
例:配偶者の遺留分
配偶者の法定相続分1/2×遺留分1/2=1/4
また遺留分侵害請求権とは、被相続人が財産を遺留分の権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分の権利者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することをできる権利です。
以前はこの権利は「遺留分減殺請求権」という名称でしたが、現在は「遺留分侵害額請求権」と変更されました。
その理由は、以前の「遺留分減殺請求権」では対象が全ての財産であり、例えば不動産の権利行使の場合、不動産の持分を共有することになっていました。
共有という形はかなり煩雑さを伴うことから、遺留分の請求は、原則として金銭債権の形で行われることとし、名称もそれに伴い変更となりました。
具体的に相続開始後の手続きの流れとしては以下のとおりです。
1 相続開始時の財産の価額に生前贈与した財産を加算し、債務を控除した額を算出します。
2 上記の価額に遺留分割合を乗じて算出します。
遺留分算定に組み込まれる生前贈与については10年前までの特別受益に該当するものに限定されます。
税務上の申告では3年前の贈与まで相続財産に含めることと相違するため注意が必要です。
遺留分侵害額請求の行使については単独の意思表示のみによって生じるもので、口頭でも可能となります。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。
遺言書をつくる際には、遺留分を考慮して作成する必要があります。
また、1年以内の中で相続人の確定から財産の確定、遺留分の計算に至るまで意外と時間がないことから生前から相談できる窓口を家守会ではご用意しております。
お問い合わせお待ちしております。
遺留分とは、被相続人の財産を相続するに際して一定の法律上保証されている遺産の最低割合のことを指します。
残された相続人の生活保障であり生計一にしている方を守るための制度となっております。
遺留分は遺言書より優先されるため、遺言書で相続する財産がなくとも、その権利を主張できます。
例外として兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分を主張することができません。
計算方法としては、相続分の半分を遺留分として計算します。
例:配偶者の遺留分
配偶者の法定相続分1/2×遺留分1/2=1/4
また遺留分侵害請求権とは、被相続人が財産を遺留分の権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分の権利者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することをできる権利です。
以前はこの権利は「遺留分減殺請求権」という名称でしたが、現在は「遺留分侵害額請求権」と変更されました。
その理由は、以前の「遺留分減殺請求権」では対象が全ての財産であり、例えば不動産の権利行使の場合、不動産の持分を共有することになっていました。
共有という形はかなり煩雑さを伴うことから、遺留分の請求は、原則として金銭債権の形で行われることとし、名称もそれに伴い変更となりました。
具体的に相続開始後の手続きの流れとしては以下のとおりです。
1 相続開始時の財産の価額に生前贈与した財産を加算し、債務を控除した額を算出します。
2 上記の価額に遺留分割合を乗じて算出します。
遺留分算定に組み込まれる生前贈与については10年前までの特別受益に該当するものに限定されます。
税務上の申告では3年前の贈与まで相続財産に含めることと相違するため注意が必要です。
遺留分侵害額請求の行使については単独の意思表示のみによって生じるもので、口頭でも可能となります。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。
遺言書をつくる際には、遺留分を考慮して作成する必要があります。
また、1年以内の中で相続人の確定から財産の確定、遺留分の計算に至るまで意外と時間がないことから生前から相談できる窓口を家守会ではご用意しております。
お問い合わせお待ちしております。

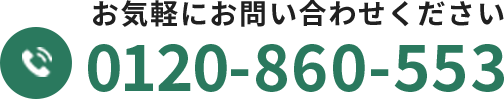
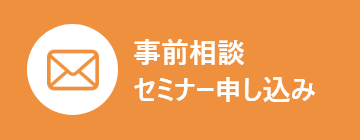


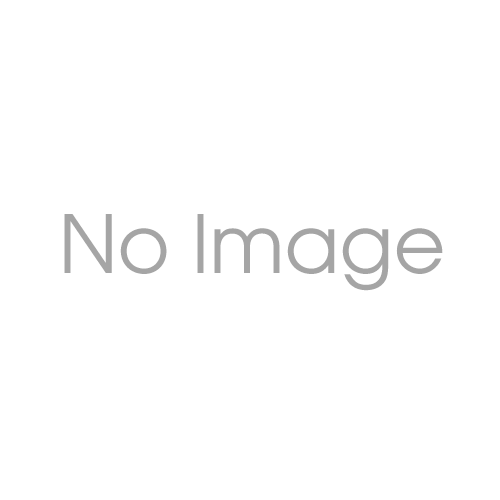 (1)_page-0001.jpg)
サテライト三筑モデルルーム内覧会チラシ_page-0001.jpg)
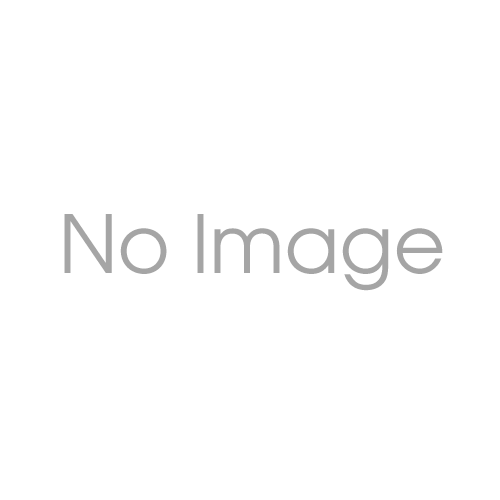_page-0001.jpg)