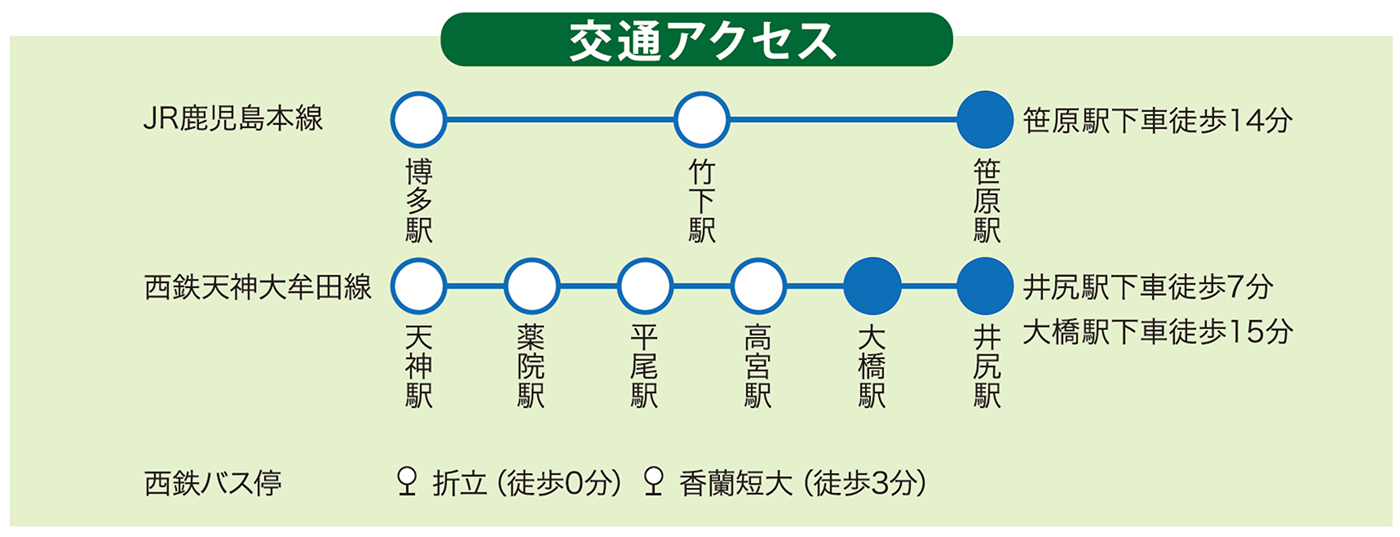特別受益

特別受益
特別受益とは、相続人の内特定の人が、被相続人から受けた遺贈又は婚姻や養子縁組、もしくは生計を守るためにうけた贈与のことです。
例えば、居住用の家を贈与した場合や教育資金を払ってもらった場合、独立開業資金など特定の者が資金援助を受けた場合や経済的利益を得た者などが該当します。
特別受益がある場合は、被相続人が相続開始のときの財産の価額に当該特別受益の価額を加算したものを相続財産とみなします。
また特別受益を受けた相続人については、相続分の中から自身の特別受益を控除した残額が相続分となります。
例:配偶者1人 子A 子B(特別受益者)
相続財産1億 特別受益2,000万円
みなし相続財産1億+2,000万円
配偶者 相続分 1億2,000万円×1/2=6,000万円
子A 相続分 1億2,000万円×1/4=3,000万円
子B 相続分 1億2,000万円×1/4-2,000万円=1,000万円
上記のように特別受益は相続財産の前渡しの性格を有していることがわかります。
遺産分割によって相続人全員が同意すれば特別受益を考慮しないことも可能です。
なお、特別受益は遺産分割に影響を与えますが、相続税の計算では考慮しません。
そのため、上記の例では遺産分割の対象は1億2,000万円ですが、相続税の対象は1億円となります。
(ただし、遺贈・死因贈与や相続開始前3年以内の贈与は、または相続時精算課税を利用していれば、相続財産に加算されます。)
特別受益に基本的に該当しないものとしては、以下のとおりです。
・生命保険金
・死亡退職金
・婚資
・学資
特別受益の持ち戻しの免除について、被相続人が贈与契約書や遺言などに記載している場合は相続財産に組み入れずに計算も可能です。
相続税法改正により配偶者相続人に特別受益があった場合「持ち戻し免除の意思表示」があったと推定されるのは以下のとおりです。(民法第903条)
・婚姻期間が20年以上の夫婦のうち、一方が被相続人となり他方の配偶者に対して遺贈または贈与をした場合
・遺贈又は贈与が、居住の用に供する建物またはその敷地を対象としている時
持ち戻し期間が2019年法改正により10年という期限が設定され、それ以前のものについては持ち戻しの対象から除外されました。
10年前から被相続人の相続財産が相続人へ承継されているかどうかの判断を亡くなったあとに判断することは難しいことが多いです。
家守会では会員様の資産状況を確認しながら推定相続人の方々との個別相談を行っております。
お問い合わせお待ちしております。
特別受益とは、相続人の内特定の人が、被相続人から受けた遺贈又は婚姻や養子縁組、もしくは生計を守るためにうけた贈与のことです。
例えば、居住用の家を贈与した場合や教育資金を払ってもらった場合、独立開業資金など特定の者が資金援助を受けた場合や経済的利益を得た者などが該当します。
特別受益がある場合は、被相続人が相続開始のときの財産の価額に当該特別受益の価額を加算したものを相続財産とみなします。
また特別受益を受けた相続人については、相続分の中から自身の特別受益を控除した残額が相続分となります。
例:配偶者1人 子A 子B(特別受益者)
相続財産1億 特別受益2,000万円
みなし相続財産1億+2,000万円
配偶者 相続分 1億2,000万円×1/2=6,000万円
子A 相続分 1億2,000万円×1/4=3,000万円
子B 相続分 1億2,000万円×1/4-2,000万円=1,000万円
上記のように特別受益は相続財産の前渡しの性格を有していることがわかります。
遺産分割によって相続人全員が同意すれば特別受益を考慮しないことも可能です。
なお、特別受益は遺産分割に影響を与えますが、相続税の計算では考慮しません。
そのため、上記の例では遺産分割の対象は1億2,000万円ですが、相続税の対象は1億円となります。
(ただし、遺贈・死因贈与や相続開始前3年以内の贈与は、または相続時精算課税を利用していれば、相続財産に加算されます。)
特別受益に基本的に該当しないものとしては、以下のとおりです。
・生命保険金
・死亡退職金
・婚資
・学資
特別受益の持ち戻しの免除について、被相続人が贈与契約書や遺言などに記載している場合は相続財産に組み入れずに計算も可能です。
相続税法改正により配偶者相続人に特別受益があった場合「持ち戻し免除の意思表示」があったと推定されるのは以下のとおりです。(民法第903条)
・婚姻期間が20年以上の夫婦のうち、一方が被相続人となり他方の配偶者に対して遺贈または贈与をした場合
・遺贈又は贈与が、居住の用に供する建物またはその敷地を対象としている時
持ち戻し期間が2019年法改正により10年という期限が設定され、それ以前のものについては持ち戻しの対象から除外されました。
10年前から被相続人の相続財産が相続人へ承継されているかどうかの判断を亡くなったあとに判断することは難しいことが多いです。
家守会では会員様の資産状況を確認しながら推定相続人の方々との個別相談を行っております。
お問い合わせお待ちしております。

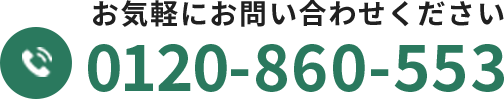
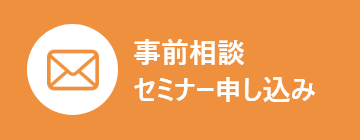

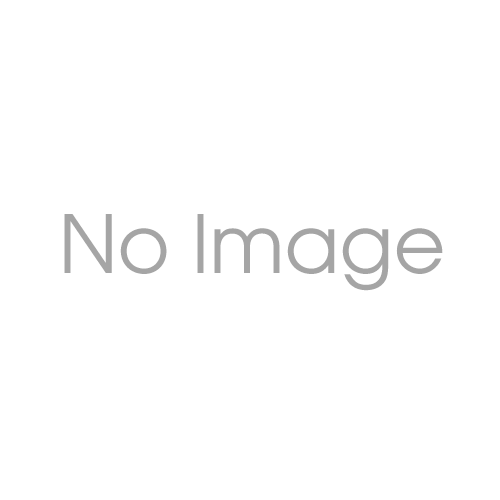 (1)_page-0001.jpg)
サテライト三筑モデルルーム内覧会チラシ_page-0001.jpg)
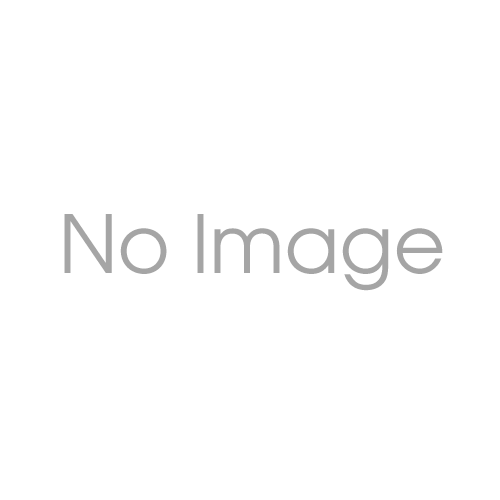_page-0001.jpg)